4年生の算数の授業に行ってきました。3桁のわり算の筆算の勉強でした。昨日は2桁だったので、桁が1つ大きくなりましたが、解き方の理屈は一緒です。
その中で、例えば「108÷12」という問題がありました。ちょうど児童が問題を解くところを見ていると、商のところに「4」と書きました。これは、商の見当をつけることができていない証拠です。大体の見当をつけるためには、考えやすいだいたいの数に置き換えて考えるとよいのです。108はおよそ100、12はおよそ10と見れば、「100÷10」と考えることができ、そうすれば「商はだいたい10くらい」という見当をつけて計算にとりかかることができます。先日の4年生の授業で、「見当をつける」ことについて学習していましたが、これは他の学年でも知っていてほしい計算の基本的なテクニックの1つと言えます。
それからわり算の筆算の中にも、「わる数×商」というかけ算が出てきます。計算に苦手意識をもっている子たちは、この部分でも苦労している様子が見られました。例えば「69×7」のような計算では、一般的には一の位、十の位の順にかけ算の計算をしていくわけですが、くり上がりの数を書かなかったり、何も書かないまま頭の中ですべてを計算しようとして、何度も間違えてしまう様子が見られました。これも、計算の工夫ということで何年生かで学習するのですが、69×7=(70-1)×7と考えれば、70×7=490というのは簡単に求められるので、特に複雑な計算をしなくて済むわけです。筆算をしなくても、490から7を引くくらいの計算なら簡単にできますので、これも計算が苦手な人が無駄に複雑で面倒な計算をしなくても答えを導くことができるテクニックの1つと言っていいでしょう。
その他にも、372のような数字の各桁の数を足した数が3の倍数になるとき(3+7+2=12)には、その数字は3の倍数(3で割り切れる数)と言えるなど、知っているととても役に立つテクニックがあります。そういうコツが分かれば、きっと今よりは問題が解きやすくなるのではないかと思います。授業を見ながらそんなことを思いました。
ちなみに、次の写真は3年生の算数のテストの様子で、記事の内容とは特に関係ありません。が、テストの内容をよく見てみると、同じようにわり算の単元のテストとなっていました。
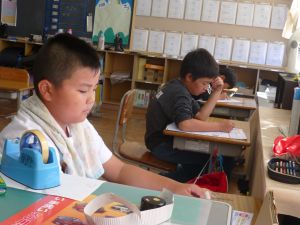



ちなみに、こうした計算の学習においては、同じような問題を数多く反復練習するような場面がよく見られます。面倒だなとつい思いがちかもですが、これにはちゃんと理由があると私は思います。クラスには、計算が苦手で間違いやすい人もいれば、概ね計算の方法を理解しだいたい正確に解答できる子、ゆっくり考えながらであれば計算ができる子など、いろいろな子がいます。苦手な子は反復練習をしてたくさんの練習に触れてたくさんの練習の経験を積むことが当然大切だと思いますし、比較的計算が得意な子の中にも、うっかりミスをしやすい子が見られます。また、ゆっくりなら計算できる子も、テストなどの際に限られた時間内に全てを正確に解かなければならないという場面になると、慌ててしまって力を出し切れないという例もよく見られます。つまり、やり方を理解してできるようになった子は、限られた時間でも、どんなに問題があっても、素早く正確に解けるような力をつけていくと、テストの中でも慌てることなく問題を解くことができるようになります。こうした意味で、一定の反復練習は誰にとっても大切であることは間違いありません。
「こんなにたくさんの計算練習、面倒だな」「適当にやっちゃえ」と思うこともあるかもしれませんが、自分の課題を意識して一生懸命練習する人と、ただ終わらせればよいと思って適当にやってしまう人では、同じ問題を練習していても大きな差が出てしまいます。同じ問題を同じ量だけやっていても伸びていく人は、そういう「意識」をしっかり持っているからだと思います。大変だなと思う学習や宿題でも、どうせなら自分の力を高めるための練習にして欲しいと思います。
